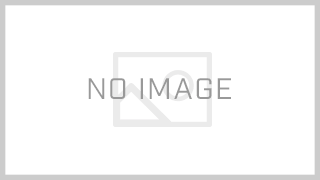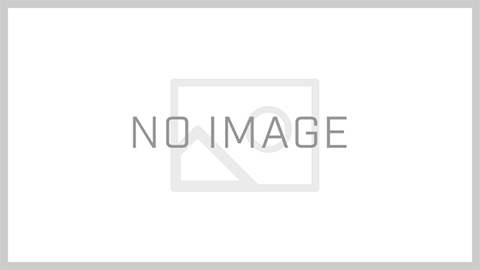わ〜た〜な〜、べ~よ~いち(渡部陽一)です!
先日、戦場カメラマン渡部陽一さんのお話を伺ってきたyamadaです。
大きなモーション・ジェスチャー、ゆったりとしたお声。
感情がこもっていることこの上なし!
相手に「伝えよう」という意識がビンビン伝わります。
お話も、身振り・手振りも、完全にミュージカルです(笑)
(本当にモーションが大きい!)
この記事では、戦場カメラマン渡部陽一さんから伺った
- 渡部陽一さんが戦場カメラマンになって25年。なぜになったのか?
- 戦場で犠牲になるのはいつも子供。その実情は
- 渡部陽一さんが仕事をすすめるうえで大切なのは〇〇が8割
をまとめています!
contents
渡部陽一さんはなぜ戦場カメラマンになったの?

渡部陽一さんは、現在45歳。
学生で20歳のときにきっかけがあったそう。
授業でアフリカ大陸のなかでは、今でも言葉がわかるチンパンジーが暮らしていると聞いた。
その一帯にはピグミー族の方々がくらしている地域。
渡部陽一さんはその生活を聞いて、ピグミー族に興味がわき
「直接お話を伺ってみたい!」
と思って、アルバイトで貯めていたお金でさっそくアフリカに飛んだそう。
好奇心の強さ、行動力。
そして、アルバイトでコツコツお金をためていたというところも
渡部陽一さんらしい~。
でも、実際にアフリカに飛んでみると…出逢ったのは戦場の子供たち
現地では小さな子どもたちが銃を持って戦っている。
血だらけで渡部陽一さんの服を引っ張り助け下さい!と。
当時20歳の渡部陽一さんは子どもたちを助けることは出来なかった。
「何か出来ることはないか?」
「子供のころ好きなカメラを生かして、戦場の子どもたちの声を届けよう。」
この青年渡部陽一さんにとっての出会いが戦場カメラマンになるきっかけだった。
それから戦場を25年間まわってきづくことは、
「戦争している国同士では、戦争を止めることはできない。」
ということ。
だから、第三国、日本でも、国連でもいい。手を差しのべること。
手を差し伸べる…まずは具体的に何ができる?
渡部陽一さんが考えるのは、それはまず、相手のことを知ること。
「1つだけでもいいから。」
相手のことを1つ知るだけでも怖くなくなる。
世界が変わるきっかけになっていく。
では、戦争なんてなくなればいいのに。
日本のように家族と買い物に行って、暮らす。
そんな国はまだまだ少ない。
渡部陽一さんが見てきた戦場の子ども達とは
イラクで武装した兵士が常にいる写真

イラクでは、武装した兵士が自宅の前に。
子どもたちは怯えて、怒ってもいたという。
戦争が起きる一番大きな理由は、石油!
スマホも、車も、パソコンも全て石油から成り立っている。
イラクには石油が埋まっている。
外国は石油を要求、イラクが開発が不十分で渡せないと回答すると、
武力行使も辞さないと脅し、戦争になった
秘密裏にイラクに打ち込まれた劣化ウラン弾
劣化ウラン弾が秘密利に撃ち込まれていた。
イラクの空気、土、水に劣化ウランが散らばった。
当時生まれた子どもたちは、
- 首に悪性腫瘍がある男の子
- 右目がない女の子
- 生まれながら白血病の男の子は痩せ細って家族の前で死んでいった。
戦争の犠牲者はいつも子どもたちだ。
一歳の赤ちゃんが足を石の固まりにロープでぐるぐるに結ばれた写真。
場所はインド。
経済発展著しいインドだが貧しい農村の家族が都市部に移住、両親が働いている間、赤ちゃんを建設解体現場にくくりつける。ぐるぐる回るしかできない。
輝くインドを支える影だ。
病院も戦争で爆発され薬は燃えてしまっていた。
パキスタンの中学生の女の子がつづったブログ
世界では、子供が教育を受けられない地域がまだまだ多い。
特に女の子は宗教上禁止されることも。
パキスタンもそんな国の一つ。でも、中学生のある少女がブログにそんな現状をつづり、こっそり学校にも通っていた。
過激派組織にブログを辞めるように脅されても書き続けた。
いずれ過激派のメンバーが彼女の中学生をつきとめ学校に押し入った。
「ブログを書いた奴はお前か」
銃弾2発が彼女の頭へ打ち込まれた。
しかし、奇跡的に緊急手術により一命をとりとめた彼女。
彼女はノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさん。
彼女の主張、
- 戦争は武器で止めるものではない
- 一本のペンと、一冊の教科書と一人の先生がいれば、子どもたちの生活を変えていくことができる。
- 子どもたちの基礎教育の基盤をつくることができる。
- 世界を変えていく力は教育にある。
それを渡部陽一さんも伝えようとしている。
戦争の最前線では、食料も、薬も、毛布も不足している。
それでも生きていけるとしたら、
家族が一緒にいること。
家族がいれば少しの食糧も、薬も分けあえる。助け合えるから。
渡部陽一さんの戦場カメラマンとして仕事術は、あらゆる職種に大切な理論

戦場カメラマンといえば、一人で戦場に入り危険な場所で写真を撮る。
一人でインタビューもし、危険極まりない仕事。
そんなイメージがあったけれど、実際には違うそう。
伺ってみると、一般のビジネスマンのように用意周到に準備する仕事の実態が分かった。
段取りが8割、戦場での撮影は2割
戦場には決して一人では入らない。
- その国、取材に入る地域で生まれ育ったガイドさん
- その国の言葉のアクセントまで扱える通訳さん
- 身辺警護をしてくれるセキュリティ
- そしてカメラマン渡部陽一さん
少なくとも4人以上の取材チームを結成するそう。
仕事の8割が危機管理に関すること。
戦場カメラマンの本分だとイメージされる戦場での撮影技術、立ち回り方、インタビューの技術は、2割に過ぎない。
ガイドさんの言うことは絶対厳守。
「もう何度も取材に行っているか大丈夫」と無理をしたりはしない。
- 安全が第一。
- 取材はその次。
だそうだ。
これこそプロフェッショナルではないでしょうか。
そういえば、ピーター・ドラッカーが
医者も、営業マン、教師も、すべての職種で仕事の仕方のの8~9割は同じ。
といったことを著書で述べているの思い出します。
“戦場カメラマン”という特殊な仕事のようで、段取りが8割、その大半が危機管理に労力が費やされる。
- ビジネスマンでも、
- 看護師でも、
- 教師でも、
実際にその職種で輝ける仕事ばかりができるわけではありません。
その8割とか大半は地味な仕事。どちかというやりたくない仕事かもしれない。
一流は、ためらわずに雑用、地味な仕事にも注力できるものだと思いました。
たしかに、カウンセラー、メンタルコーチの仕事にしても、
実際にクライアントのお手伝いに割ける時間って全体の労力からすると一部。
マネジメント、自己研鑽、クライアントにお会いするための準備が大切。
日本で、住む家があり、食べるものがあり、働くこともできるってとても幸せなことですね。
ほんの少しでも感想をいただけると嬉しいです^^